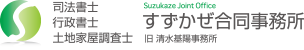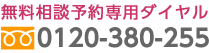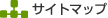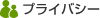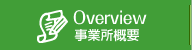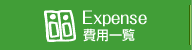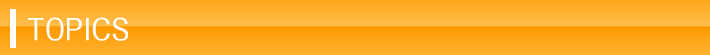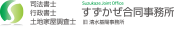TOPICS
知って得する法律豆知識!「相続放棄の受理通知書と受理証明書」
更新日付 2025.08.01
こんにちは。
司法書士の大桃です。
*
ついに8月に突入しましたね。夏真っ盛りです。
7月後半は異常な暑さでしたが、誰も体調を崩すことなく元気に働いております。
8月は年に一度の社員旅行もありますので、この勢いで夏を乗り切りたいと思います。
*
*
さて、本日は「相続放棄の受理通知書と受理証明書」についてです。
相続放棄の期限内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、裁判所から「相続放棄受理通知書」と題する書面が送られてきます。
基本的には、この受理通知書のコピーを債権者に提出することにより、「自分は相続人ではありません。」という証明をすることになります。
*
また、家庭裁判所からこの受理通知書が送られてきた際に、必要であれば受理証明書の請求をしてください、という案内書きが記載されています。
昔は、受理通知書は法務局で相続登記をする際の添付資料として使えなかったので、必ず受理証明書を取得して添付しなければなりませんでした。
その取り扱いも変更になり、受理通知書で相続登記ができるようになったので、現在は受理証明書を取得することはほとんどなくなりました。
お客様には、もし受理通知書を無くしてしまったときには受理証明書を請求してください。と伝えています。
*
*
とはいえ、一点気を付けなければならないことがあります。
それは相続財産の中に負動産(土地)があるときです。
*
被相続人の負債や税金の滞納なんかは、時間の経過により時効で消滅します。
それに対し、土地だけは相続放棄をしてから何十年経過したとしてもそのまま残り続けます。
*
家庭裁判所の記録の保管期間は30年間です。それ以降は記録がないので受理証明書を取得することはできません。
もし、30年以上の時が流れて当事者の世代交代が起きた後に不動産に関する問題が生じたときに、相続放棄受理通知書を紛失していた場合、相続放棄をしていた事実を証明する手段が無くなってしまうということです。
きちんと受理通知書を引き継いでいれば問題は起きないのですが、心配な方は証明書を複数通取得して保管をしておくのも一つの選択肢かもしれません。
*
今日は以上です。
最新の記事10件を表示
- 2025.12.26司法書士の日常㉝「年末のご挨...
- 2025.12.17年末年始の営業日のお知らせ
- 2025.10.27スタッフブログ【98】「駐車...
- 2025.10.23市民後見人養成講座【江別市成...
- 2025.10.10スタッフブログ【97】「ぜひ...